マンションの大規模修繕で、修繕委員会を設立しようとしている方!
その時、運営細則をどうやって決めたらいいか?
お悩みかと思います。
この記事では、修繕委員会設立時の運営細則のポイントを解説しています。
私の場合、マンションの住民に詳しい専門家がいませんでした。
管理会社主導で大規模修繕を進めていくしかない、と思われたいた矢先、提示された修繕見積もりは超高額!
専門家なしでも、何とか自分達で大規模修繕を頑張ろうと思い、調べたことを中心に記載しています。
※大規模修繕はマンションの資産価値を大きく左右します!!
他人任せにしないように注意しましょう!!
こちらも参考にして下さい!「【忙しい人必見!】大規模修繕の単価」
1.書式テンプレートをダウンロードして、ポイントを変更する!
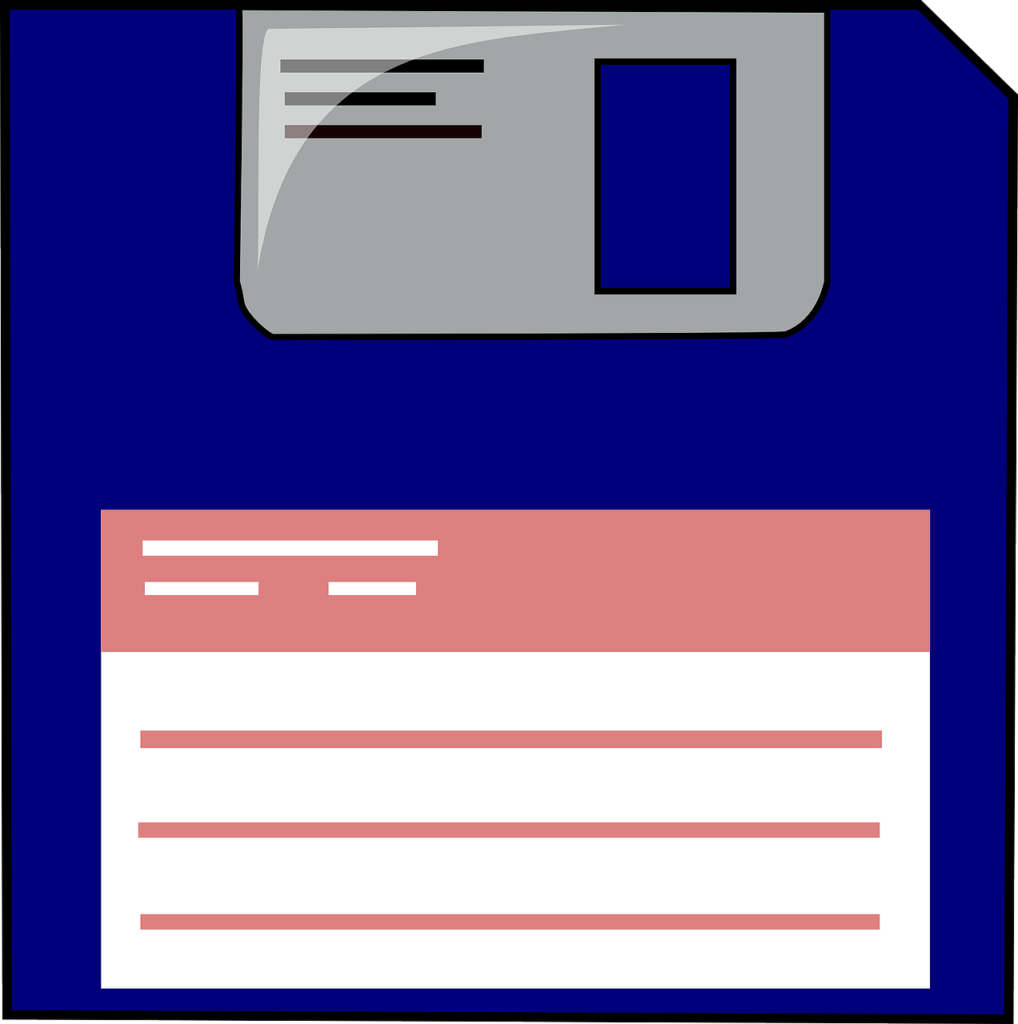
Clker-Free-Vector-Images / Pixabay
修繕委員会立ち上げを考えているときは、マンション管理士などの外部専門家に相談する前だと思います。誰に相談して、運営細則を規定すればいいのか?
ホームページ上を検索すれば、PDFなどでサンプルがダウンロードできますので、それを参考に使いましょう。
インターネットで「修繕委員会 細則」と検索すると、某マンションの細則や、国から指定を受けた機関が準拠する細則モデルなどがヒットします。
ただ、ネット上の情報では信頼性に欠ける、という方もいると思いますので、念のため、管理会社からも書式を取り寄せましょう。(書式がない、という管理会社など、話になりません。)また、マンション管理センターでは、年間利用料3,085円で書式が手に入ります。
修繕委員会立ち上げ時に、相談できる専門家がいない。でも、大丈夫です。検索してみれば分かりますが、そこまで複雑ではありません。
運営細則を定める第一歩として、まず、書式をダウンロードしましょう。
もしコンサルタントを探しているなら・・・【忙しい方必見!】大規模修繕のコンサルタントとは?
2.自分のスタイルに合わせて、ポイントとなる箇所を変更する!
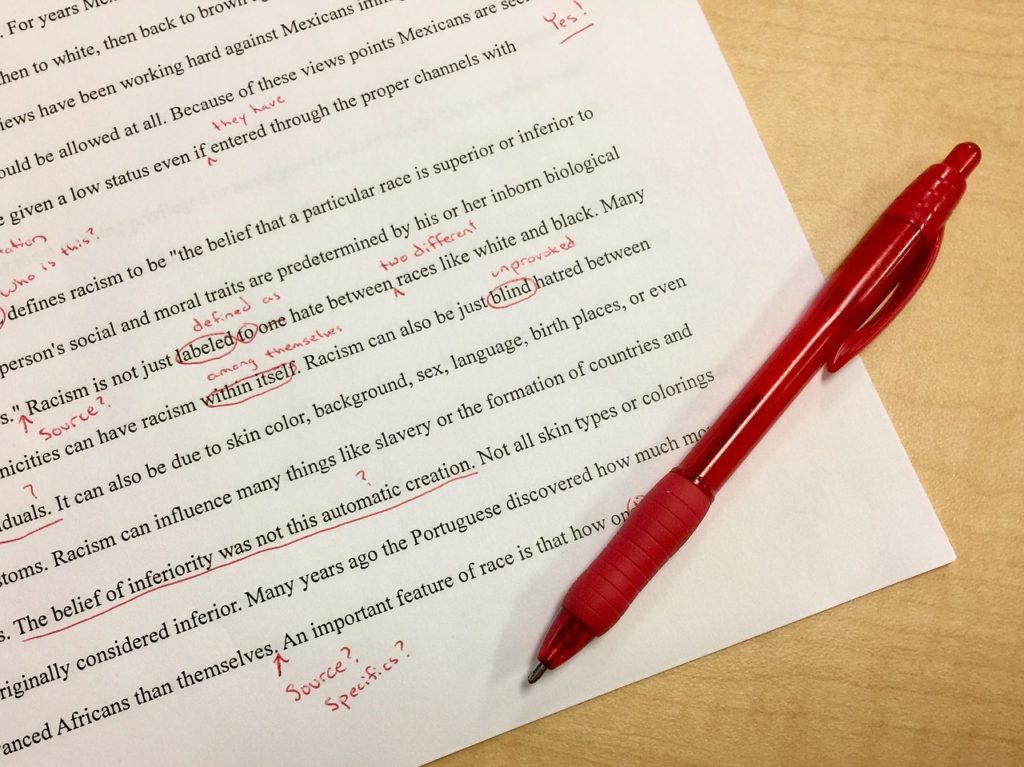
annekarakash / Pixabay
マンション大規模修繕の修繕委員会(または専門委員会)は、必ず設立する必要があるものではありません。
修繕委員会はマンション居住者がメンバーとなります。集まらない場合は、管理会社主導での大規模修繕となります。
それを避けるためには、自分達で何とかするしかありません。運営細則については、次のポイント別に、手に入れた書式を変更していきましょう。
2-0.運営細則のポイント
2-1.権限範囲
「理事会の諮問機関」であることを明記しましょう。
権限を逸脱しないように注意する、つまり、修繕委員会には、物事を決断する権限はない旨を明記しておきましょう。
※修繕委員会は、理事会から調査等を依頼され、報告した内容(答申、と言います。)が採用されるかは、理事会が決める、という建付けです。
※理事会開催時の注意ポイント:理事会は委員会に対し、諮問事項と内容を具体的に示すことが必要です。
2-2.人数
・メンバーは多数決に備えて、奇数が望ましいです。
・少なくとも、「委員長」・「副委員長」・「書記」を選定しましょう。(戸数の1〜2割の人数が一般的です。)
・メンバーは交代制ということも可能です。例えば、1か月交代で書記を交代していく 等です。
・権限の集中を避けるため、理事長と委員長との兼務できないようにしましょう。
・実質の役割は、リーダー役、実務役、広報役、連絡役に大まかに分類できます。(連絡役は理事会や住民との橋渡し役です。出来れば、理事会から1名選んでもらいましょう。)
2-3.任期
・委員会の常設化を想定しない場合は、「業務が完了した時に理事会決議により当該専門委員会は解散」との文言を明記しましょう。
(大規模修繕は約12~15年スパンなので、常設化しない方がいいかと思います。)
2-4.業務内容
・主な業務は、下記のものがあります。
①建物診断の実施
②大規模修繕の設計
③費用と予算の調整
④施行業者・監理者の選定
⑤定例打ち合わせ・検査への出席
⑥工事終了後のフィードバック
※施工業者との窓口、住人のクレーム対応や相談窓口、住民への説明会、アンケート実施 等も、修繕委員会が対応する場合があります。
負担を考えて、場合によっては、理事会にも一部の業務を割当てましょう。
※検査への出席などは、サラリーマンには平日は難しいため、平日でも出席可能な方にも委員になってもらうとよいでしょう。
※委員の負担や勤務先(建築会社の方などがいて、業者選定の際に選べなくなってしまう場合)などを考慮して、必要に応じて、業務範囲を制限する文言を入れましょう。
例:施行業者選定には関与しない 等
2-5.経費精算、報酬
報酬額や経費の支払い方を細則に定めるのが望ましいです。
(経費の種類や上限 など。ただし、報酬は必ず定める必要はありません。)
2-6.委員会の意思決定方法
委員会内部での意思決定方法についても、運営細則に規定しておきましょう。(多数決が一般的かと思われます。「過半数超で決議」など。)
3.総会で決議してもらいましょう!

cdu445 / Pixabay
運営細則を作成するだけではダメです。
運営細則は総会の普通決議事項(理事会の決議事項の可能性もある)ですので、総会に上程し、決を取りましょう。
これで、正式に修繕委員会の運営細則が制定されることになります。
※ちなみに、修繕委員会の発足は、理事会での決議が一般的です。
4.まとめ
以上のことをまとめますと、
・運営細則のテンプレート入手
・自分のスタイルに合わせて修正
・総会で決議を取る
という大まかな流れになります。
特に大事なポイントは、業務内容と任期です。
サラリーマンをしながらの方は、特に無理な負担にならないよう、業務範囲の広げ過ぎに注意して、理事会にも協力を仰ぎながら、運営細則案を作成していきましょう。


