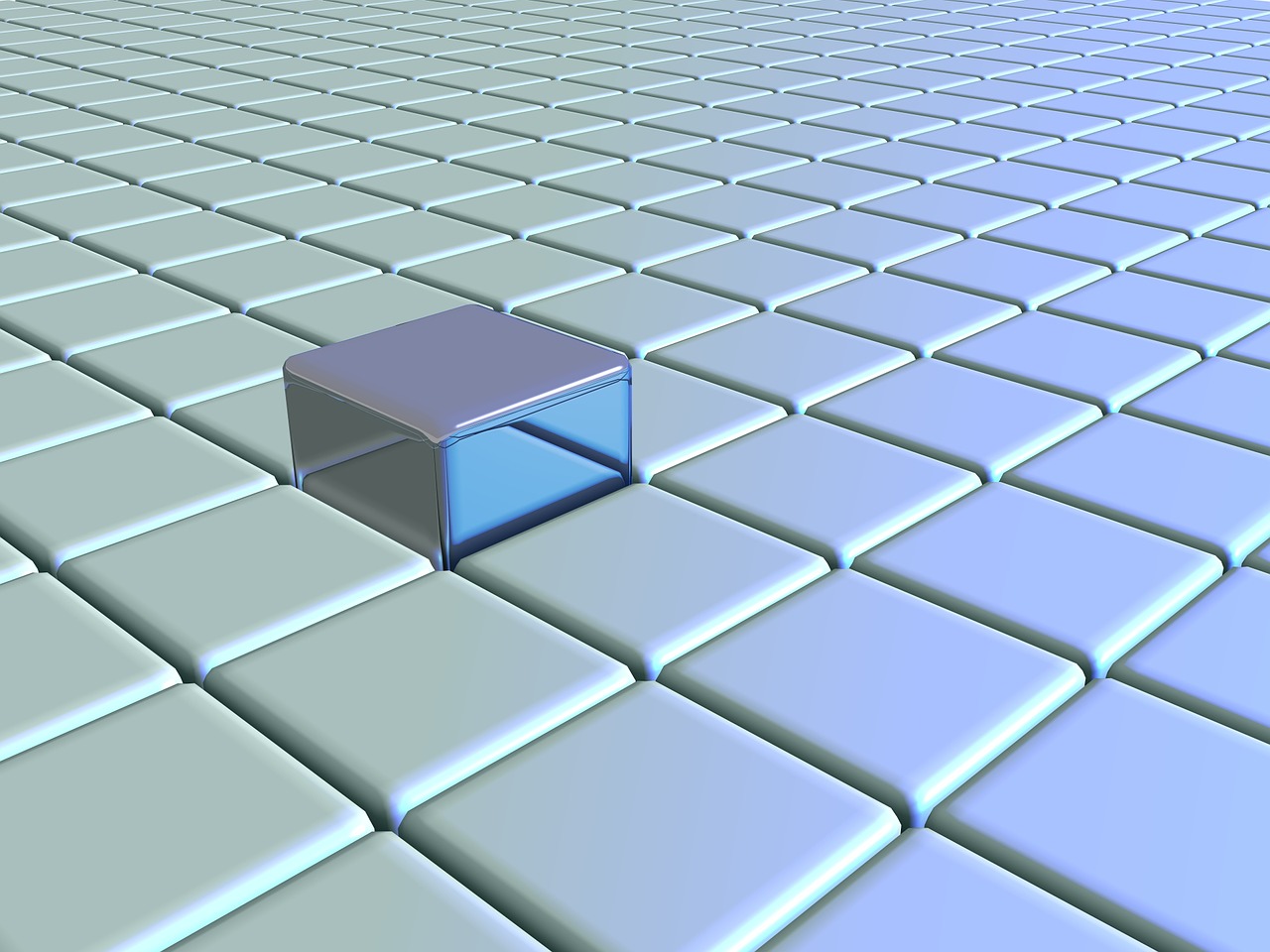大規模修繕を控えている方!
修繕委員会に立候補しようかと悩んでいる方!
来期、理事会の輪番が回ってくる方!
コンサルタントに大規模修繕工事の一部を任せるかどうか、悩んでいませんか?
この記事では、コンサルタントとは、そもそもどういうものか、を解説しています。
私のマンションは総戸数が30戸弱で、建築に詳しい住民もいませんでした。
そのため、大規模修繕は管理会社主導で計画が立てられましたが、なんとコンサルフィーが19%!
後日、調査した結果、19%の中には、コンサルフィーに分類されない費用も入っていました。
単純にコンサルタント、というだけでも業務内容は幅があります。
自分たちのマンションには、どの業務が必要で、不要なのか。この点をしっかりと把握した上で、上手にコンサルタント探しをしましょう!
1.コンサルタントの目的
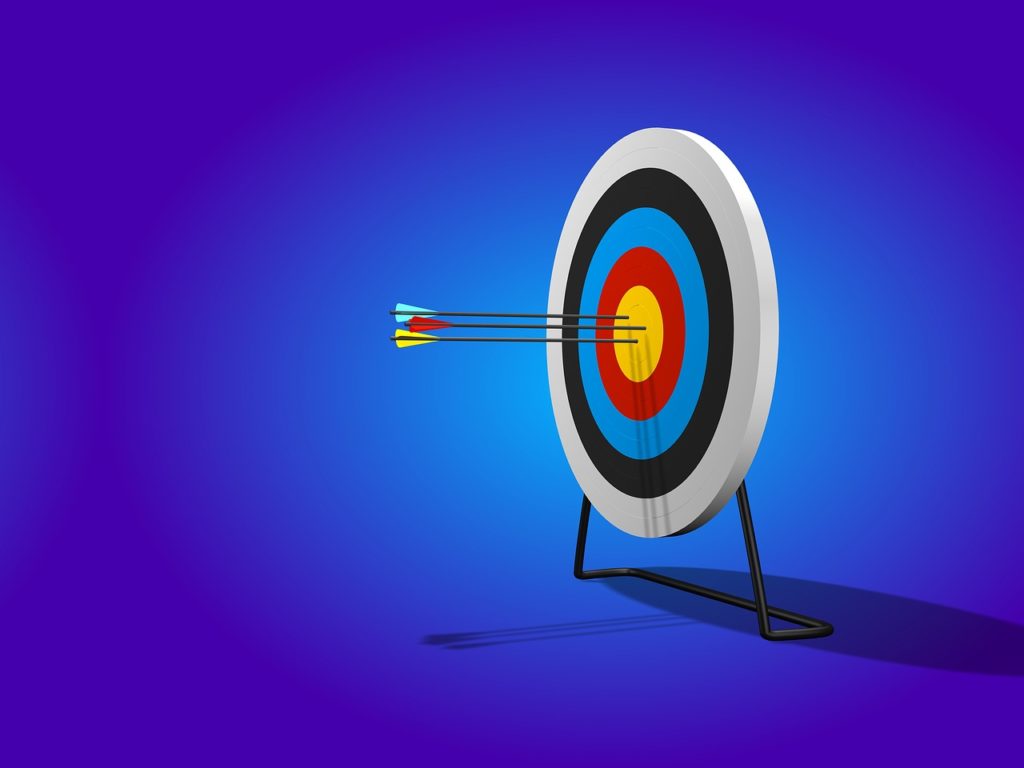
QuinceMedia / Pixabay
コンサルタントを導入する目的のキーワードは、「第三者的立場」です。
つまり、コンサルタントを入れることで、次のことが達成できるはずなのです。
①大規模修繕工事の検討過程の透明性と公平性を確保することができる。
②管理組合の利益を保護することができる。
コンサルタント会社を、複数社から絞る時など、この目的に立ち返り、考えるようにしましょう。
2.コンサルタントを行う会社

sasint / Pixabay
コンサルを行う会社種類は、一級建築士事務所、管理会社、コンサル会社(マンション管理士の事務所など)があります。
昔は施工業者自身が設計・監理もしていましたが、最近では責任分担の観点から、設計・監理のスペシャリストとして、第三者的な立場で一級建築士事務所などがコンサルに入るケースが増えてきています。
3.コンサルタントの具体的役割
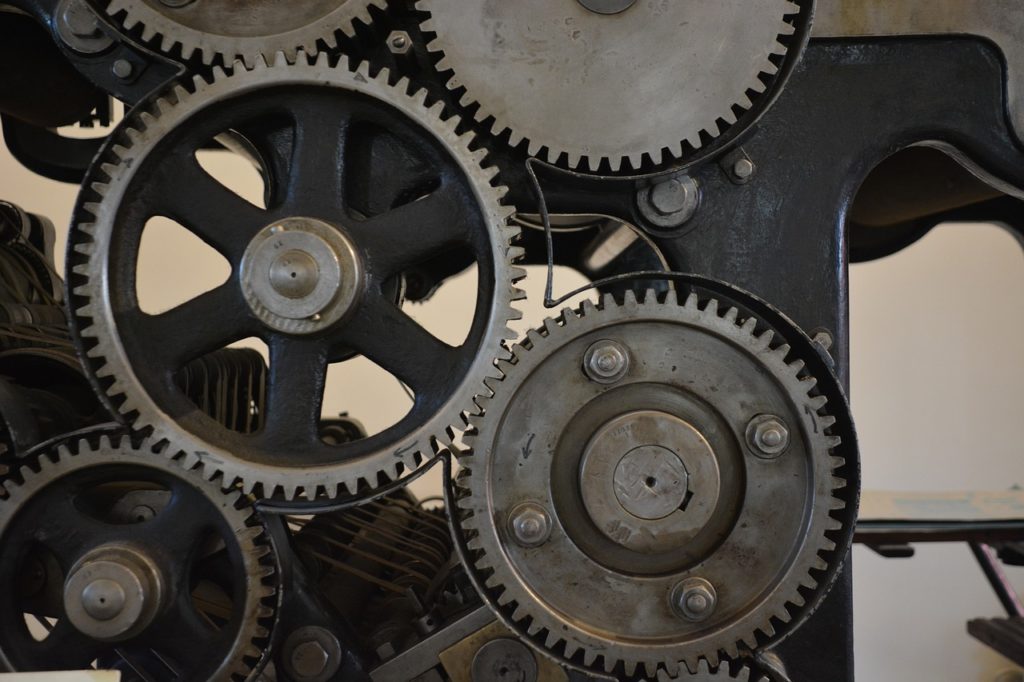
fsHH / Pixabay
一口に「コンサルタント」と言っても、仕事内容は幅広いです。
主な役割として、次のようなものが挙げられます。
①大規模修繕工事とは直接的な関係がないこともある業務
・定期的建物調査
②大規模修繕工事の前に行うこと
・長期修繕計画の策定
・修繕工事用の建物診断
・修繕計画・予算の策定
・設計図書の作成
・施行業者選定サポート
③工事中および工事竣工後に行う業務
・工事監理
・アフター点検等のサポート業務
4.コンサルタントのフィー水準の目安

ArtisticOperations / Pixabay
コンサルティング業務として代表的と考えられる業務は、「設計図書の作成」、「施工業者選定サポート」、「工事監理」です。
特に「設計図書の作成」と「工事監理」を合わせて、「設計監理」と呼ぶことが多いです。
この業務は、例えば施工業者選定のための競争入札の基準になる設計図書を作成する業務も含まれているため、大規模修繕において非常に重要な業務です。
また、第三者の目線から工事を監督する「工事監理」業務も、いわゆる手抜き工事などを防止するために、重要な業務となっています。
逆に考えると、管理組合だけの力では、実施することが難しい業務とも言えます。
(設計監理のフィー水準としては、工事費の概ね3~5%が多いと言われています。)
また、「施工業者選定サポート」も、コンサルティング業務の代表的な業務です。
具体的には、業界専門誌などで工事業者を公募して、先ほどの設計図書を基準として入札し、あらかじめ定めた選定基準に基づき、工事業者の選定をサポートする業務です。
(フィー水準としては、先ほどの設計監理料と合わせて、工事費の10%前後が目安のようです。ただし、総合的なサービス込の水準なので、メニュー内容を吟味することが重要です。)
5.まとめ
コンサルティング業務として考えられるものは幅広くありますが、実態としては、建物診断だけ行ったり、工事業者選定までで業務を終了するケースもあるようです。
その場合、アフターフォローを施工業者が行うケースもあります。
いずれにしても、コンサルタントの業務範囲を理解し、理事会または修繕委員会との間で、適切な業務の割当てを行えるようにしましょう。
また、業務範囲により、適切と考えられるフィー水準も大きく変わってくるため、業務内容を良く確認するようにしましょう。