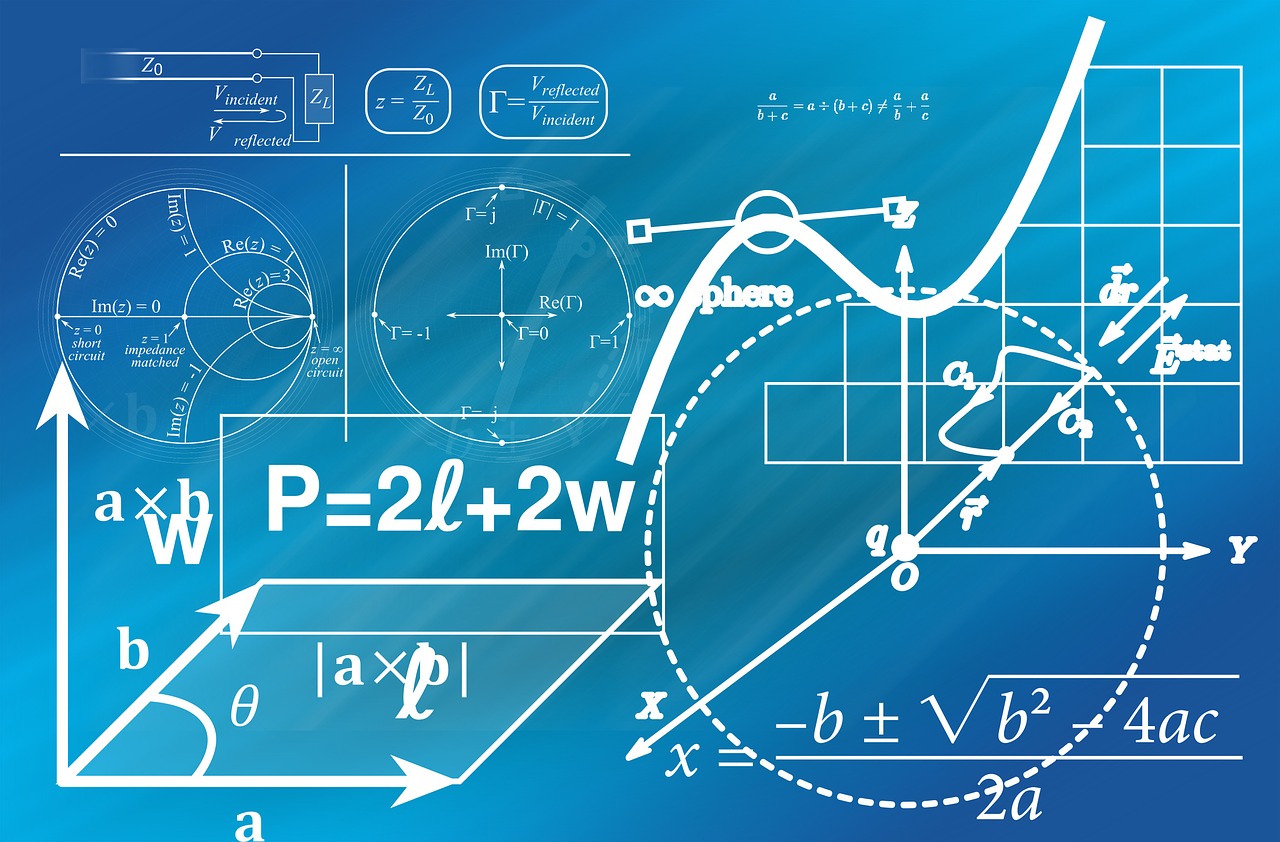「路線価」って聞いたことありますか?
この「路線価」を使って、土地の価格が分かることはご存知でしたか?
この記事では、「路線価」から土地価格を計算する方法をまとめています。
1.路線価を使って土地価格を計算
1-1.計算前に最低限の路線価に関する知識を
「路線価」とは、簡単に一言にしてしまうと、
道路「沿い」の土地価格
です。
(「路線」の価格だから、道路の価格、というわけではありません。あくまで、「土地」の価格です。
ですから、「建物」の価格でもありません。
路線価には2種類あります。
固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の計算に使う「固定資産税路線価」
と
相続税や贈与税の計算に使う「相続税路線価」
があります。
一般的に「路線価」と言う時は、「相続税路線価」のことを言うことが多いです。
路線価の良いところは「この道路に接している土地は1平米いくら」と道ごとに細かく指定してあるところです。
1-2.路線価を使って土地の評価額を計算する方法(相談税路線価の場合)
繰り返しになりますが、路線価は、
道路「沿い」の土地価格
です。
土地価格(土地の時価)を求める計算式です。
(基本的な式です。難しくすれば、もっと細かい式もありますが、専門家でなければ必要ありません。)
なぜ、路線価に土地の面積を掛けるのか。
それは、路線価が、1平米当たりの価格だからです。
土地の面積は売買契約書や登記事項証明書、チラシに書いてあります。
また、最近はグーグルマップでも測定できます。
路線価は、インターネットで取得できます。
路線価は「円」単位でなく、「千円」単位で公表されていますので注意して下さい。
(末尾のアルファベットは気にしないで下さい。「借地権価格」を求める際に使用します。)
「1,000B」と書いてあれば、
「1,000円」ではなく、
「1,000,000円」です。
「÷ 0.8」とは、路線価を時価の水準にするための計算です。
詳細は後述していますので、そちらをご参照下さい。
例えば、路線価が、
1,000B
と記載されていて、
土地の面積が、
100平米
だったとすると、
1,000(千円/平米) × 100平米 ÷ 0.8 = 125,000,000円
1億2,500万円になります。
1-3.路線価を使って土地の評価額を計算する方法(相談税路線価がない場合)
インターネットで相談税路線価を調べようと思っても、見つからない時があります。
「倍率地域」と書かれていたり、何も書かれていなかったりします。
そんな時は、
「固定資産税」路線価
を使います。
相談税路線価と同じサイトで調べることができます。
固定資産税路線価を使って、土地価格を求める時も計算式はほとんど同じです。
1つだけ、「÷ 0.8」が、「÷ 0.7」になります。
計算式は、
となります。
「0.8」が「0.7」になる点を注意して、後は相談税路線価と同じ使い方で、ほぼ問題はありません。
(厳密には少し違いますが、それは専門家が気にするレベルの話です。)
2.計算した価格で売れるのか?
結論から先に書きますと、
ほとんどの場合には売れます
と言えます。
「ほとんどの場合」以外の例外に該当してしまう場合は、後ほど注意点として説明します。
例外に該当した方は、不動産鑑定士に相談された方が良いと思われます。
(宅建業者や税理士の場合、裁判になった場合などに不十分だからです。)
他のサイトなどでは、
路線価から計算した価格から○○%〜○○%の間で売れる可能性が高い
などと説明しているものを良くみかけます。
良く考えると、それって当たり前のことだと思いませんか?
例えば、単価の低い500mlのペットボトルのジュースだって、コンビニとスーパーとドラッグストアでは価格が違いますよね。
会社からの帰り道に寄ったコンビニで手軽に買いたい
とか、
少し家から離れているけど、一番安く売っているドラッグストアまで買いに行く
とか、
賞味期限に近いタイムセールで50%を狙いにいく
とか、人それぞれに、様々な事情があって、様々な価格が存在するものだと思います。
そもそも、路線価の根拠となるのは、不動産の価格に関する専門家である不動産鑑定士の分析と判断です。
ですから、公的な機関(相談税路線価は国税庁)が公表しているのです。
つまり、
路線価から求められた時価を、売買の際の判断基準にすれば、
安く売りすぎたり、
高く買いすぎたり、
という悪い結果を防げる、ということです。
3.そもそも「路線価」とは何か?
繰り返しになりますが、「路線価」を簡単に一言で言い表すと、
道路「沿い」の土地価格
ということです。
あくまで、「土地」の価格のため、「建物」の価格は含まれていません。
路線価には、
「固定資産税路線価」
「相談税路線価」
の2種類があります。
「固定資産税路線価」は、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の計算に使われます。
「相談税路線価」は、相続税や贈与税の計算に使われます。
3-1.相続税路線価とは?
相続税路線価とは毎年7月頃に国税庁から公表される土地価格の指標です。
公表は7月ですが、年の始めである1月1日時点の土地価格です。
地価公示による「公示地価」の8割の水準です。(つまり、時価の80%です。地価公示については、後で説明しています。)
主に市街地を中心とした道路に面する土地の、1㎡あたりの単価で表示されています。
(千円単位です。)
路線価は、土地を相続又は贈与した場合に、税金を計算するための重要な指標です。
そのため、
実際の売買事例
公示地価
不動産鑑定士の鑑定評価
などを細かく調べたうえで決定されています。
相談税路線価は、国税庁のホームページなどで見ることができます。
3-2.固定資産税評価額とは?
東京23区は東京都から、それ以外は各市町村から公表されます。
3年ごとに、公表される年の1年前の1月1日時点の土地価格です。
地価公示による「公示地価」の7割の水準です。
(つまり、時価の70%です。地価公示については、後で説明しています。)
3-3.地価公示による公示地価とは?
「地価公示」で公表される価格(「公示地価」といいます。)は、国土交通省から発表される土地価格です。
相談税路線価や固定資産税路線価と同じく、建物価格は含まれません。
毎年1月1日時点の価格が、その年の3月に公表されます。
「公示地価」は、
というものです。
参考までに定義を引用します。
(出典:大辞林第三版)
(時価の定義は様々なのですが、この記事では分かりやすく、シンプルにするために、上記の定義のイメージで話を進めます。)
そして、先ほども説明しましたが、相続税路線価は、公示地価の80%の水準です。
逆算して、相続税路線価を80%で割ると(割戻、といいます。)、地価公示の水準になります。
(固定資産税路線価の場合は、70%になります。)
まとめますと、
時価=公示地価=相続税路線価÷80%
時価=公示地価=固定資産税路線価÷70%
(ただし、土地価格のため、建物価格は含まれない。)
ということになります。
ちなみに、「公示地価」、いわゆる「土地の時価」は、
「不動産鑑定士」という専門家により、分析・判定されます。
(「不動産鑑定士」が判定した時価は、裁判資料となったり、法人の意思決定の際に使われたりと、様々な場面で活用されています。)
お菓子とか新車などは、
「定価」
があるので、「時価」が分かりやすいです。
(コンビニよりも、スーパーの方が安い、というのことはありますが。)
ところが、不動産、とくに「土地」の価格には、誰から見ても分かりやすい「定価」というものが存在しません。
だから、専門家である「不動産鑑定士」が、
もし今、売買されたら………
という視点で、土地の「時価」を判定します。
これが「公示地価」です。
(不動産鑑定士以外の人が出した価格は、「時価」とは認められません。注意しましょう。)
4.路線価で土地価格を計算する時の注意点
先ほど、
路線価で計算した価格で売れる
路線価で計算した時価は売買の判断基準になる
と言いました。
ただ、それには例外があります。
その例外を以下、注意点として列挙します。
(該当する場合は、専門家に対して相談されることをお勧めします。)
・土地面積が大きい場合
・都会のど真ん中の土地
・生産緑地
順番に説明します。
4-1.バブル時期
路線価や公示地価は毎年1月1日時点の土地価格のため、随時、更新されるわけではありません。
ですから、例えば激しいバブルで土地価格が急騰した場合や、リーマンショックなどにより景気が急速に冷え込んだ場合など、その年の1月1日時点と12月31日時点の価格には開きがある可能性が非常に高いです。
もし、そのような時は、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。
(会社経理関係で不動産価格を間違えてしまうと、色々と大変なことになります。)
4-2.土地の面積が大きい場合
土地の面積が大きい場合、面積に比例して計算後の価格も大きくなります。
多くの場合、路線価の周りの土地よりも2倍や3倍、ましてや10倍くらいある土地の場合は、計算した土地価格から20〜30%(多い時は50%ほど)価格が下がる傾向があります。
また、逆にプレミアがつくような場合はプラスになることもあり、土地が大きい場合には、価格が非常にブレます。
ですから、路線価の周りの土地と比べて、計算しようとする土地が大きい時は要注意です。
4-3.都会のど真ん中の土地
都会のど真ん中の土地は、路線価で計算した価格とは異なることが多いです。
なぜなら、そのような土地は、不動産というよりは、投資の対象となる金融商品に近い場合があるからです。
そのような場合は、路線価をベースに計算するのではなく、賃料などの収入ベースで、金利などを考慮した利回りによって価格を求める必要があります。
(専門用語で「収益価格」と言います。)
ただ、この計算には、詳細な取引情報や高度な建築に関する知識などが必要となりますので、都会のど真ん中の土地をお持ちの方は、専門家にご相談されることをお勧めします。
4-4.生産緑地
生産緑地とは、非常にざっくりと言えば、
のことです。
生産緑地は「500平方メートル以上」の土地であること、と法律により決められています。
ですから、場所によっては、前に説明した「土地の面積が大きい場合」に該当します。
そして、永遠に生産緑地として、税金の優遇が受けれる訳ではなく、期限があります。
それは、「指定から30年」です。
30年経過後は、ほとんどの場合、市場に土地が売りに出される、と言われています。
現在の生産緑地の多くは、法律が改正された1992年に指定されたものが多く、2022年に30年の期限を迎え、一気に大量の土地が売りに出されることが懸念されています。
(いわゆる「2022年問題」です。)
もし、この生産緑地を持っている方でしたら、路線価で計算した価格は、信頼性に劣るかもしれません。
なぜなら、このような土地の場合、「開発法」と呼ばれる高度な価格査定方法が使われることが多いからです。
生産緑地については、専門家に相談されることをお勧めします。
5.まとめ
いかがだったでしょうか。
まとめますと、
路線価で計算した時価は、
です。
計算式も簡単です。
相談税路線価 × 土地の面積 ÷ 0.8 = 土地価格
固定資産税路線価 × 土地の面積 ÷ 0.7 = 土地価格
ただ、あくまで「土地」の価格であることに注意しましょう。
(建物価格は含まれません。)
また、以下に該当する方は、路線価での計算では正確な時価が出てこない可能性が高いため、必要に応じて、専門家である不動産鑑定士に相談しましょう。
(このような場合は、決して、路線価に基づいた価値判断を行わないで下さい。)
・土地面積が大きい場合
・都会のど真ん中の土地
・生産緑地