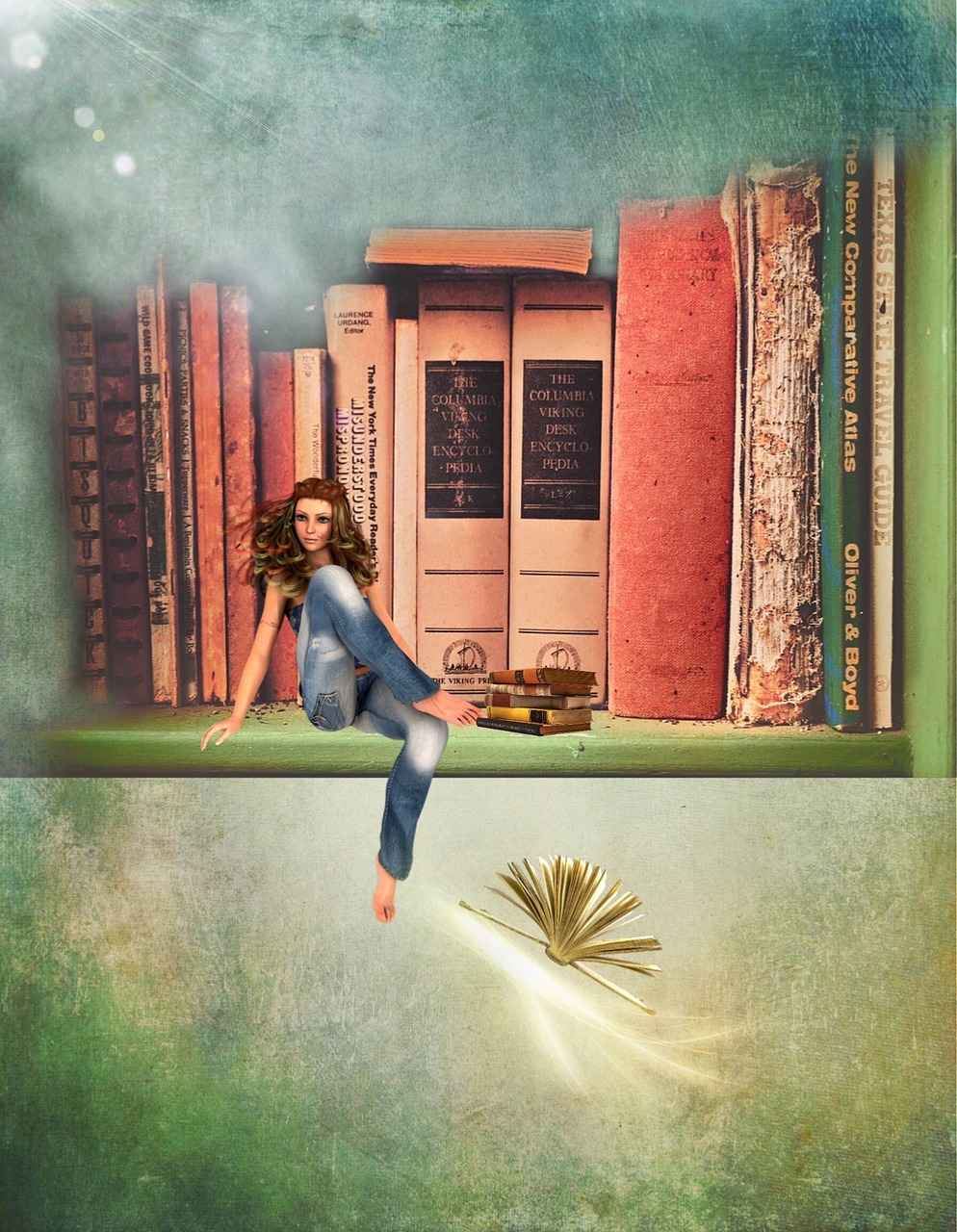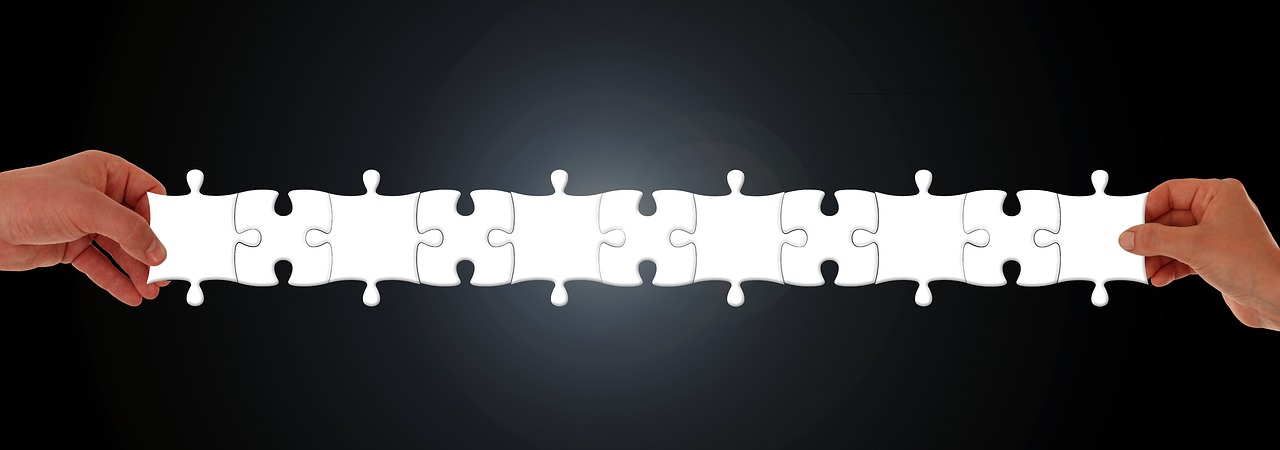「IFRS」って、最近良く耳にしませんか。
それで、「IFRS第16号」とは何であるか、どんな影響があるか、は分かりますか。
他にもIASやらIASBやら、横文字が多くて良く分かりませんね。
この記事では、IFRS第16号に関して調べたことをまとめました。
1:これまでは「IAS第17号」、これからは「IFRS第16号」
「IFRS」とか、「IAS」と言われても何が何やら分からない、という人が多いと思います。
結論から言いますと、IASとIFRSは名前が違うだけで、中身は同じものです。
なぜなら、どちらも作成者が同じだからです。(目的は当然同じです。)
IAS(InternationalAccountingStandard)は日本語では「国際会計基準」と訳されます。
また、IFRS(InternationalFinancialReportingStandard)は日本語では「国際財務報告基準」と訳されます。
IASを作成した国際会計基準委員会(IASC)が、2001年4月に国際会計基準審議会(IASB)になりました。
IASCがIASBになった後に作成したものがIFRSです。
つまり、例えれば、製造元の名前が変わったので、商品の名前も変わったが、商品自体は同じ、そんなイメージで宜しいかと思います。
2:IFRS第16号の目的とは?
IASBとFASB(米国財務会計基準審議会)は、2016年1月13日、IFRS第16号「リース」を公表しました。
そもそも、このIFRS第16号を作成した主旨とはどのようなものでしょうか。
現在では、共通の会計基準のもと、よりグローバルに企業の業績の比較を行えるようにと、IFRSへ会計基準を統一しようとする動きが加速しています。
そんな中、リースに関する会計基準に関しては、アメリカと日本はオンバランス処理とオフバランス処理の2つの処理方法を、認めていました。
今回のIFRS第16号でリース基準を改訂した主旨は、主に以下の2つです。
借手によるオフバランス処理をなくすこと
単一のリース会計モデルを開発すること
つまり、日本とアメリカのように、現行ではオンバランスとオフバランス処理の2つの会計モデルが存在している国に対して、オンバランス処理の会計モデルへの1本化を迫る内容となっています。
3.ほぼすべてのリース契約がオンバランスに
では、IFRS第16号が適用されることによって、何が変わるのか。
まず1つ目の変化としては、今までオフバランスで良かったリース契約を、オンバランスしなくてはいけなくなります。
オンバランスとオフバランスとは、そもそも何か。
会計の目的は、企業の業績を報告することにあります。
オンバランスとオフバランスを、無理矢理一言で言ってしまうと、次のような感じです。
オンバランスとは、しっかりと報告すること
(貸借対照表、という書類に記載して報告します。)
オフバランスとは、企業の業績を良く見せるために、報告しないこと
(オフバランスにすることで、ROAという総資産利益率の数字が良くなり、より儲かっているように見えます。不動産でいう利回り、のようなイメージです。)
また、リースの定義が、IAS第17号よりも、IFRS第16号の方が広くなります。
日本(IAS)では、今まで「形式的」なリース契約の判断が行われていました。つまり、リース契約や賃貸借契約、という形式面や数値基準などに照らして、リース契約か否かを判断していました。
これに対して、IFRS第16号では、「実質的」にリースかどうかを判断することになります。
つまり、契約や数値などの形式面ではリース契約ではないように見えても、実質的にリース契約の内容である場合には、IFRS第16号ではリース契約と判断されます。
日本ではオンバランス処理されてこなかったリース契約も多く、IFRS第16号の適用により、財務諸表上の資産と負債が大きく増加する、と言われています。
(先ほどの例で言えば、単純にROAが悪化する方向に作用する、ということです。)
4.IFRS16号と借地権
IAS17号(旧リース基準)では、「実質的」に売買と同じならオンバランス、「実質的」にも賃貸ならオフバランス処理でした。
「実質的」とは、具体的な数字の基準があります。
細かいことは書きませんが、要は売買価格の9割近い賃料を払っている時や、借りているものの使用可能期間の8割近くを借りている時は、賃貸というよりは売買、つまり所有権を持っているのと同じでしょう、という訳です。
土地の賃貸借があります。
不動産は通常、土地と建物に分けられますが、建物は使える年数に限りがあります。(この使える年数のことを「耐用年数」といいます。)
建物の構造(木造か、鉄骨造か など)によって、耐用年数は異なります。
例えば、鉄骨造は概ね40年少しの耐用年数、と言われていますが、この鉄骨造の建物を38年リースする、つまり借りた場合を考えてみて下さい。
ほとんどの期間、借りている人が使ってます。こんな時は、「実質的」に売買したのと同じ、と考えて、売買と同じ会計処理が求められてきました。(オンバランス処理)
では、土地はどうでしょうか。
土地の耐用年数は何年か。
土地の耐用年数は「無限」と考えられています。
したがって、どう頑張っても、「実質的」に売買とは考えられません。
ですから、今までのIAS17号の会計処理では、土地の賃貸借はオフバランス処理がされてきました。
ただ、これからはIFRS17号により、「実質的」に判断されます。
例えば、土地の長期リースの場合(半永久的な旧法借地権)、賃貸の会計処理ではなく、土地を購入したのと同じ会計処理となります。
5.不動産賃貸借が見直されるきっかけに?
IFRS第16号の適用により、変化する影響として考えられるのは、不動産の賃貸借です。
先ほど、IAS第17号では、土地はオフバランス処理となる、と書きましたが、建物も契約年数などの条件により、オフバランス処理できることがあります。
ただし、耐用年数が無限と考えられている土地と異なり、建物の耐用年数は有限です。
ですから、当然、契約年数等により、オンバランスで会計処理を行わなければならない場合もあります。
しかし、IFRS第16号を適用した場合は、今までオフバランス処理できていたものでも、ほぼ全てをオンバランス処理にする必要があります。
もともと、企業の業績を良く見せるオフバランスのために、わざわざ不動産を借りていた会社にとっては、不動産を借りる意味がなくなります。
ですから、IFRS第16号の適用により、不動産の借り方自体を見直す会社が出てくることが予想されます。
なぜ、「借り方」かと言うと、例外的にオンバランスしなくてよい賃貸借があるからです。
それは短期の賃貸借です。
期間は1年未満の場合です。
ですから、企業の選択肢としては、いっそのこと売買するか、もしくは期間1年未満で借りる、などが考えられます。
6.まとめ
いかがでしたか?
横文字が多くてわかりづらいかと思いますが、まとめてみます。
そもそも、IFRSはIASBという組織で作られた会計基準のことです。
IASBは、もともとIASCという名前で発足しました。
このIASCが作った会計基準をIASと言います。
IFRSとIASは作成時期と作成者こそ違いますが、同じ目的のもとで作られたものであるため、内容的には差はありません。
そして、その目的とは、大きく2つです。
そもそも、リース会計の話をしています。
ですから、
借手のオフバランス処理をなくすこと
単一の会計モデルを開発すること
の2つが主な目的となります。
その上で、リース契約かどうか、資産計上する必要がないか、という点が問題になってくるのです。