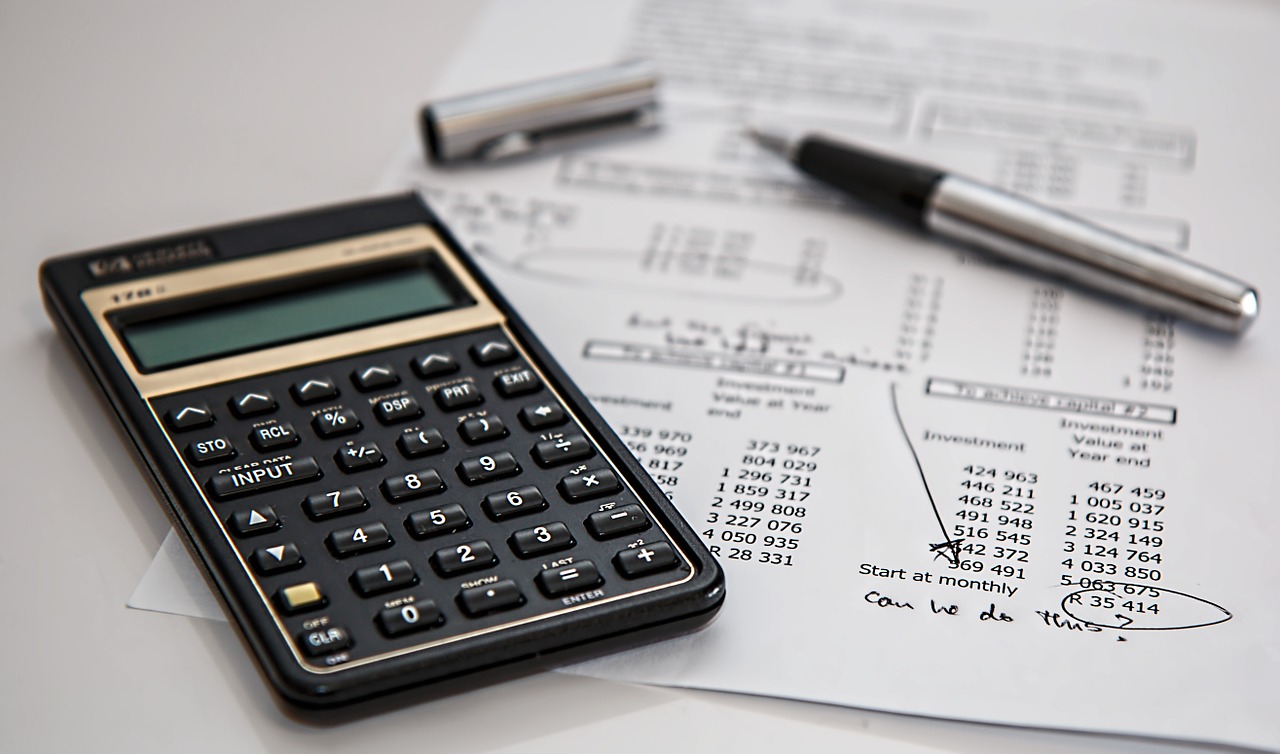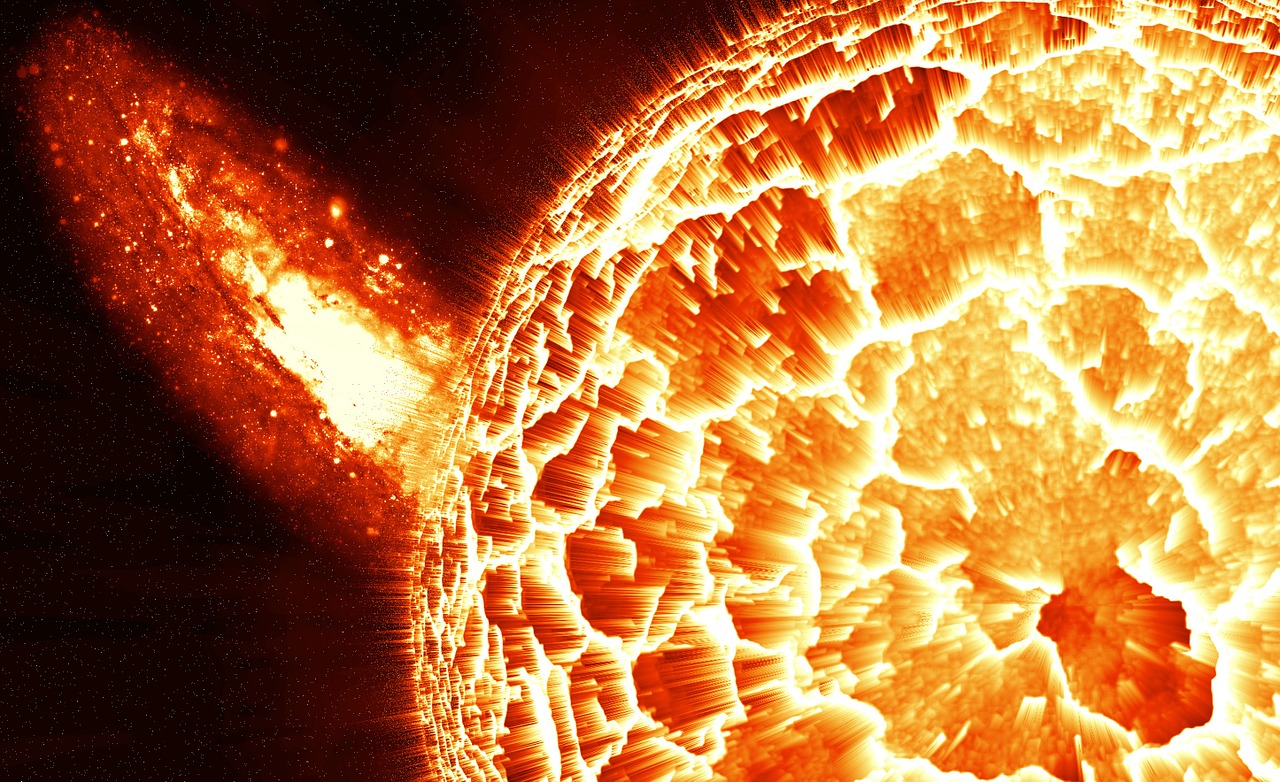最近、ソーラーパネルを良く見かけます。
このソーラーパネルで発電することを、「太陽光発電」といいます。
そして、この「太陽光発電」は、売ることができて、収入を得ることが出来るようです。
この記事では、太陽光発電による収入などの仕組みやメリットなどについて調べました。
1.太陽光発電にも種類がある:「住宅用」と「産業用」
「太陽光発電 シミュレーション」と検索すれば、地域や自宅の電気代などを入力すれば、太陽光発電による電力がいくらで売れるのか、などのシミュレーションができるサイトが一杯あります。
実際、シミュレーションをしてみると、大体のサイトで、年間の予想発電量と、その売買価格の予想値が出てきます。
ここで、発電出力の大きさによって、収入が異なりますので、注意が必要です。
設置容量が10kwを超えるか否かで、「住宅用」と「産業用」に分類されます。
※「kw(キロワット)」は設置容量といいます。これはどのくらいの出力があるか、という大きさを示す単位です。発電量を示す「kwh(キロワットアワー)」とは異なります。
10kw未満の場合は、「住宅用」に分類されます。
10kw以上の場合は、「産業用」に分類されます。
大きな違いは、設備コストと、発電した電気を全部売れるか売れないかです。
「住宅用」「産業用」という言葉からイメージして見ると分かりやすいです。
設備が大きそうなのはどちらでしょうか?
明らかに「産業用」です。
ですから、設備コストが大きいのは………「産業用」です。
また、発電した電気を全部売らない場合は、自分たちで使うことができます。
その場合、自分たちで使っても余った電気を売ることができます。
自分たちで電気を使わなくても良さそうなのは………「産業用」です。
ですから、発電した電気を全部売れるのは………「産業用」なんです。
(ただし、「産業用」でも、自分たちで使うことを選択したできます。)
また、「住宅用」か、「産業用」かによって、次で記載する固定価格買取制度の買取期間や買取価格が異なります。
2.どうやって売る?FIT〜固定価格買取制度〜
では、発電した電気をどうやって売るのか?
その仕組みがFITと呼ばれる仕組みです。
FITとは、「Feed-in Tariff」を略した英語で、エネルギーの買取価格を法律で決める、という意味があります。
日本語の方が分かりやすいと思います。
「固定価格買取制度」
といいます。
「住宅用」は2009年からスタート、「産業用」は2012年からスタートしています。
一体、どういう制度なのか?
まず、言葉から連想されるのは、
「固定価格」で、
誰かが、
「買取」をしてくれる
と予想できます。
登場人物は三人です。
電気を発電する者。
電気を買取る者。
あと一人は………
価格を決める者。
です。
具体的に言うと、
発電する者は先ほどの通り、「住宅用」か「産業用」かで分かれますが、様々いそうですよね。(個人、法人や自分で使う目的、儲け目的など様々、という意味です。)
残りの二人の登場人物は、
「電力会社」
と
「国」
です。
つまり、どちらかが、
電気を買取る者
で、残った方が、
価格を決める者
です。
ここは、買取った後どうするか、を考えると理解できます。
もし、国が買取った場合、その後どうするでしょうか?
買取った電気を国が使いますか?
それとも企業や個人に使ってもらいますか?
自分で使う、または他人に使ってもらうにしても電力会社を通さなくてはいけませんね。
なんか、この時点でワケが分からなくなりそうです。
シンプルに、電力会社が買取って、企業や法人に使ってもらう、と考えるのが分かりやすいです。
ただ、買取価格は、国が間に入って、公正に決める、ということです。
ですから、FIT「固定価格買取制度」とは、
発電者から、
電力会社が電気を買取る制度
のことです。
(注意:この後、記載しますが、永遠に買取価格が保証される訳ではありません。あくまで「一定期間」になります。)
3.ずっと買取?価格は動く?〜FITの概要〜
少し前に、永遠に買取が続く訳ではない、と言いました。
では、一体、どれくらいの期間、買取ってくれるのでしょうか。
随分前に書きましたが、「住宅用」か「産業用」かによって、買取期間や買取価格が異なる、と言いました。
ですから買取期間は2パターンです。
ちなみに、買取の対象となる電気も2パターンあります。
これも前に書いたことですが、
「全部」売るか、売らないか、です。
全部売る場合は、「全量売電」といいます。
全部ではなく、自分たちで使った後の余りを売る場合は、「余剰売電」といいます。
買取価格は、太陽光発電の容量などにより異なります。
「10kw」(設置容量)という壁で、「住宅用」か「産業用」かに分かれることになりますが、買取価格については、もう一段階、壁があります。
「2,000kw」です。
「太陽光発電 買取価格」と検索すれば、調べたい年度の買取価格の表を調べることができます。
大体、「住宅用」の方が、「産業用」より4〜6円ほど、kw当たりの単価が高いです。
理由は、「産業用」は規模が大きいことが多いので、単価を安くしても総額が大きくなるからです。
また、より規模が大きい「2,000kw」以上の場合、入札によった価格が決まります。
そのため、より買取の単価は競争により下がる傾向があります。
4.固太陽光発電のデメリット・リスク
太陽光発電のデメリットとしては、よく以下のことが言われています。
ポイントとしては、太陽光発電をする設備である「ソーラーパネル」そのものに関すること、ということです。
つまり、太陽光発電で売電収入を得るには、「ソーラーパネル」が必須です。
そのため、「ソーラーパネル」のメンテナンスは避けて通れません。
また、「ソーラーパネル」は、天候によって発電量が変わる、という特徴があります。そして、このことは発電量が不安定な可能性、というデメリットに繋がります。
また、投資対象として、太陽光発電のリスクとしては、主に固定価格買取制度に関する事項がよく挙げられています。
例えば、電力を買取る電気事業者が少ない、ということ。
また、その他にも、不動産関連の開発リスク等と同様に、近隣住民との紛争リスクや、設備の瑕疵・欠陥リスク、メンテナンスリスクなどが挙げられます。
また、電気事業者と同じく、太陽光発電の投資特有のリスクとしては、「制度」に対するリスクが考えられます。
太陽光発電の固定価格買取制度の変更権限は行政にあります。
不動産の場合、容積率などの行政的な要因が価格に与える影響はとても大きいです。
同様に、固定価格買取制度が、今後、行政により大きく変更される可能性は、投資を行ううえでリスクと考えられています。
また、ある報道などで、年々、買取価格が下がり続けることがリスク、と言われています。
これについては、買取価格が下がる一方、設備のコストなども低下しているため、費用対効果にはあまり変化はなく、リスクには該当しない、という意見もあります。
5.太陽光発電のメリット
太陽光発電のメリットも、いくつもあるのですが、その中でも「住宅用」に関して言えば、
電気代が節約できる
ことに尽きるでしょう。
また、投資用として考えた時、最長20年の間、一定の収入が期待できるという、
収入の安定性
が挙げられます。
6.まとめ
太陽光発電とは、ソーラーパネルを使って発電することです。
この太陽光発電により発電した電力は、FIT(固定価格買取制度)によって、国が定めた買取価格で、一定期間、電力会社などが買取ってくれます。
設置容量が10kw未満の場合は10年間、
10kw以上の場合は20年間です。
また、同じく設置容量が10kw未満の場合は「住宅用」、10kw以上の場合は「産業用」に分かれます。
買取価格の単価は、
「住宅用」の方が、「産業用」よりも高いです。
2,000kw以上の設置容量の場合、入札によって買取価格は決まります。
※ちなみに、10kwの太陽光発電システムを設置するのに、通常必要と言われている面積は、大体50平米弱、と言われています。
また、メガソーラー(1,000kw超の発電量)の設置のための必要面積は、10,000平米、と言われています。(野球のグラウンドの大きさです。)